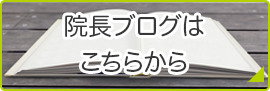ゆめのきクリニック|文京区本郷 本郷三丁目 内科 発熱外来 漢方

栄養学を勉強しています
私は栄養学の勉強をしています。栄養学セミナーにも参加しており、セミナーは大盛況ですが、医師よりも他の医療職か他業種の人が多いようです。
昔から「医食同源」という言葉があるにも関わらず、残念なことに医学部のカリキュラムのなかに栄養学はありません。
それを問題と感じることもなく長年過ごしてきてしまい、反省しながら栄養についてイチから学ぶと「目からウロコ」のことばかりでした。
私たちは食べるものでできている
“You are what you eat”という言葉どおり私たちの身体は私たちが食べたものから作られており、細胞単位でも細胞を構成する分子・原子のレベルでも、身体は常に取り入れられたものによって新しく入れ替わっています。
脳もまた食べたものから作られ機能するにも栄養が必要なので、日々の食事は思考や感情にいたるまで影響しています。
学べば学ぶほど、栄養の問題を抜きにして病気を診ることはできないと考えるようになりました。
現代における栄養学
現代はさまざまな栄養学があります。
栄養素の分類法やそれぞれの構造・性質については概ねコンセンサスが得られているようで、栄養素を身体がどう利用しているか(分解・吸収・代謝)についてはよりミクロで詳細な研究が行われており、体内動態を調べる新しい手法もいくつも開発されているようです。
多種多様な食事療法
現代の栄養学というアプローチで導かれる食事のほかに、食事療法としては古いものから新しいものまで多種多様な方法が存在しています。
個別の食品について是か非かの意見が分かれるものも多いのですが、どういう経緯なのかテレビ番組で取り上げられてブームになる食品もあります。
とくに意識していない人でも巷で騒がれているとちょっと興味がそそられたりするのではないでしょうか。
正しい栄養学とは?
いったいどういう栄養を摂れば健康になれるのか、治療としてまたはダイエットとして勧められるのでしょうか。
それはそれはたくさんの主張があり、大筋は一緒でも細かい部分では相反していたり、それぞれ“流派”が作られているように感じます。
ある食事法を提唱している人々はそれが絶対的に正しいと考えているように見え、根拠として歴史や科学のなかから自説に都合のいい部分のみを引用しているように思えます。
たとえば糖質の是非について「日本人はそもそもこうであった」という根拠を、100年前に求めたり元禄時代に求めたり縄文時代に求めたりという具合に。
それらの食事法の内容はずいぶん違っているわけですが、それぞれの方法を実践した人のなかには病気を克服した人が確かに存在しているようなのです。
そこに統計学的な検討がなくとも、治った人の肉声には説得力があります。
栄養学に絶対はない
そのような事例を見聞きすると、絶対的に“正しい”食事、万人によい食事というのはないのではないかと思ってしまいます。
おそらくその人に合う食事法はあってもすべての人に合う食事法はないのだろうと思います。
人種差はもとより、同じ食事をしていても短命な人も長生きの人もいるように個体差というものがあります。
遺伝子の差異なのか食事以外の要因なのか他の未知の理由によるのか、体質と言ってしまえばそれまでですが人によって反応は異なるものです。
何を信じるか
最も重要なのはその人自身の信念・信条に従って選択することなのではないでしょうか。
何を食べるかはどう生きるかと同義で、ある意味で信仰に近いと思うのです。
栄養が重要なのは言うまでもないことですが、逆に人は食べものだけで生きているわけでもありません。
その人の生き方、心やたましいにふさわしい食生活でなければならないのだと思います。
日々食べるものを意識していく
まずは何を食べるかについて、もっと意識的になったほうがいいと考えます。
社会的・経済的にそんな余裕がない状況に置かれている場合は仕方がないのかもしれませんが、少しでも知識はあったほうがよいと思います。
意識的になれば、その食べものが自分に合うかどうかについても見極められると思うのです。
それには“身体の声を聴く”ような能動的な働きかけと注意深さ、ひいては経験と忍耐も必要なのでしょうが、自分自身の感覚はいちばん信頼できるものになるだろうと思います。
何を食べてはいけないか
さて「何を食べるのがよいか」は本当にたくさんの説がありますが、「何を食べてはいけないか」については共通する部分が多くみられます。
「食べ過ぎてはいけない」というのも共通です。
やり方はさまざまですがファスティング(断食)の重要性も共通認識のようです。避けたほうがよいものとして下記のものが挙げられています。
- 食品汚染物質(放射性物質、残留農薬、水銀など)
- 保存料、甘味料、着色料、香料などの食品添加物(加工食品にはとくに多く含まれる)
- 鮮度の落ちた食品(カビ毒など天然の食品汚染物質が発生)
- ホルモン剤や抗生物質を投与された動物性食品
- 未精製の穀物
- 甘いもの、とくに精製された白砂糖
- 加工油脂(トランス脂肪酸を含むマーガリン、ショートニング等)
ほとんどが現代的な生活になってから登場したものです。
私たちの身近な食品には不自然なものがたくさん含まれており、ひとつひとつの危険性は小さくとも複合して蓄積していくと考えると、ほんとうに気が滅入ってしまいます。
あまり神経質になるともはやストレスだけが増して何も食べられなくなってしまうので、できる範囲のところで相対的に危険性を減らすようにして折り合いをつけるしかなさそうに思います。
自分の食事と自分を取り巻く世界
何を食べるかを考える際には、自分のことだけでなく、世界全体、地球全体への視点を忘れてはならないのではないでしょうか。
1頭の牛を育てるのにどれだけの農地が必要か、そこで穫れる作物を食べることにすればどれだけの人数をまかなえるか、という話があります。
肉をもっと食べましょうと言う人は、世界のすべての人がその食事をしたらどうなってしまうかを考えたことがないのかもしれません。
その作物を栽培するに当たって環境に多大な負荷をかけているとしたら?
その動物性食品を作るためにあまりにも暴力的な手段がとられていたら?
その食品が手元に届くまでにどのような方法がとられているか、すべての食品について事実を把握するのは困難ですが、本当はそんなことまで考えなければいけないと思うのです。
姪がネットのどこかで拾ってきた言葉ですが「人間は本来、戦って勝てる相手しか食べられない」・・なるほどな~と納得しました。
命をいただいている、という謙虚さは忘れてはいけないと思っています。