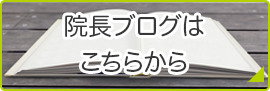ゆめのきクリニック|文京区本郷 本郷三丁目 内科 発熱外来 漢方

コレステロール
低下医療について
コレステロールのイメージ
コレステロールについて、たいていの人は漠然と「高いとよくない」というイメージをお持ちではないでしょうか。
コレステロールを下げると銘打った食品やサプリメントはたくさん出回っているし、周囲に薬を飲んでいる人もいるし…。
様々な議論が進行、正解のない状況
コレステロールと動脈硬化については新しい知見から検査で調べられることも多くなってきています。
しかし基準値については以前からずっと、論争とも呼べるほどに異なる意見があり、いまだ合意は得られていません。
コレステロール低下薬使用の是非についても正反対の意見があります。
コレステロールの重要な働き
コレステロールは多様な働きをする、生体になくてはならない成分です。
- 1.全身すべての細胞の細胞膜の構成成分である。
細胞膜によって独立した領域を作り、細胞膜を通じて物質やエネルギーを出し入れしている。 - 2.性ホルモンや副腎皮質ホルモンの原料になる。
性ホルモンは性機能に関係し、副腎皮質ホルモンは炎症の抑制やタンパク・糖質の代謝に関係している。 - 3.胆汁酸の成分になる。
胆汁酸は肝臓でコレステロールから生成され、脂肪の消化・吸収に関与している。 - 4.神経細胞のミエリン鞘という組織を形作り、脳からの迅速な情報伝達に関与する。
- 5.骨代謝に関わるビタミンDの原料になる。
最近ではコレステロールは細胞と細胞を接着させるタイトジャンクションという機構にもかかわっており、ここが破綻すると細菌やウィルスが体内に侵入することを許してしまい、慢性炎症の発症に関係するという報告があります。
コレステロールと動脈硬化の関係
動脈硬化から脳卒中や心筋梗塞が引き起こされるわけですが、高LDLコレステロール血症も動脈硬化の原因になるとされており、薬を使ってでも下げておいたほうが予防になるとされています。
動脈硬化の生じるメカニズム
日本動脈硬化学会HPのQ&Aコーナーでは、動脈硬化の生じるメカニズムについてごく簡単に説明されています。
「LDLコレステロールが増えると、LDLが血管に沈着し、酸化変性されて動脈硬化を起こします。」
文節にわけて考えると
- ①LDLコレステロールが増える
- ②LDLが血管に沈着する
- ③酸化変性される
- ④動脈硬化を起こす
となりますが、②の前に①とは直接の関係がない“血管内皮細胞の機能が障害される”という段階があります。
この段階は炎症や酸化ストレス、高圧・乱流となった血流などの要因が複数絡み合って生じるのでたいへん複雑ですが、糖尿病・高血圧・喫煙・高脂肪食・ストレス・加齢、などが関与することになります。
それを契機としてLDLが血管に沈着して(②)そこで酸化LDLというものに変化し(③)、酸化LDLを処理しようとして白血球の一種であるマクロファージが集まり、マクロファージが酸化LDLを取り込むと泡沫細胞に変化して動脈硬化であるプラークという塊を形成します(④)。
それが炎症性物質を産生したりさまざまな因子によって増大した結果、血管内腔を狭めたり、破綻して血栓を生じたりして症状を引き起こすのです。
LDLコレステロールが多いというだけで、動脈硬化を引き起こすわけではない
上記の機序から、LDLコレステロールはわかりやすく“悪玉”コレステロールと呼ばれることもありますが、単純に多いというだけで動脈硬化が引き起こされるわけではないのです。
またLDLにはサイズと密度の異なるものがあり、血管に沈着(②)しやすく酸化しやすい(③)のは小型で高密度のLDLということがわかってきました。
量より質が問題という考え方です。
この小型高密度LDL(small,dense LDL)は測定することが可能ですが健康保険の適応外です。
“超悪玉コレステロール”という名称で扱っている健診施設はあります。
また酸化LDLも測定可能であり、糖尿病患者さんの一部では保険適応になっています。
メカニズムからはこれらのほうが動脈硬化を反映するのではないかという気がしています。
今後の検討が待たれますが、現在の主流となっている、LDLコレステロールの値をもって薬で管理する医療とは直接結びつかないため、普及しないのではないかとも思います。
2つのコレステロールのバランス
LDLコレステロールはHDLコレステロールとのバランスが重要といわれています。
HDLコレステロールは不要となったコレステロールを回収して肝臓に戻す働きがあるために“善玉”コレステロールと呼ばれたりもしますが、それぞれ違う役割を果たしているということです。
HDLコレステロールが低値だと冠動脈疾患のリスクが高くなり、高値だとリスクは低くなるといわれています。
コレステロールの基準値についての論争
〈日本動脈硬化学会による動脈硬化性疾患予防ガイドライン〉より
| LDLコレステロール | 140mg/dl 以上で高コレステロール血症、 120~139mg/dl で境界域高コレステロール血症 |
|---|---|
| HDLコレステロール | 40mg/dl 未満で低コレステロール血症 |
〈人間ドック学会による判定区分〉
| LDLコレステロール | 60~119 正常、120~139 軽度異常、 140~179 生活改善で経過観察、59以下と180以上 要医療 |
|---|---|
| HDLコレステロール | 40以上 正常、35~39 生活改善で経過観察、34以下 要医療 |
正常範囲拡大の改正案もあったものの、採用されず
2014年にLDLコレステロールについて新基準値への改正案が出されましたが、採用されずに現在に至ります。
改正案では正常範囲を男性で72~178、女性では30~44歳61~152、45~64歳73~183、65~85歳84~190、と年齢別に設定し、正常範囲が大幅に拡大される形になっていました。
それまでの基準ではドック受診者の48%が軽度異常~要医療とされてしまうからです。
当時、ドック学会の改正案はメディアでも報じられ物議をかもしましたが、けっきょく新基準値は健康な受診者のデータを解析しただけのものとされ、動脈硬化学会から猛反撃にあったためか採用されませんでした。
〈日本脂質栄養学会2010年発表の長寿のためのコレステロールガイドラインより〉
- コレステロール摂取量を増やしても血清総コレステロール値(TC)は上がらない。
- 植物性の油は、がんや心疾患を防げない。
- 家族性高コレステロール血症(遺伝的に若年からコレステロールが高くなる)を一般論にしてはいけない。
- スタチン(日本で開発され現在も普及しているコレステロール降下剤)では心臓病を減らせない。
- 脳卒中は総コレステロール(TC)が高いほうが予防できる。
- オメガ6系脂肪酸を減らしオメガ3系脂肪酸を増やすことで動脈硬化やその他の病気を防ぐことができる。
コレステロール論争
2010年、脂質栄養学会は主流派に真っ向から対立する意見を発表したため“コレステロール論争”と呼ばれる様相となりました。
基準値ありきで画一的な薬物治療がおこなわれる傾向に対し警鐘を鳴らす目的があったと思われ、現在もその主張を支持する人は多いと思います。
この“論争”に対して中立的な立場からの意見を以下にご紹介します。
〈臨床研究適正評価教育機構(J-CLEAR)のコメントより抜粋〉
- 高コレステロール血症から動脈硬化性疾患の発症リスクには性差があり、女性では男性よりリスクが低く、閉経後においても約10年は発生しにくいとされている。男女別の基準値、更年期以前と以降の基準値を提示する必要がある。
- コレステロール値は低いほどよいとする根拠は、高血圧や糖尿病などリスクの高い症例や、すでに狭心症などがある症例での研究に基づいている。リスクの低い一般住民にまで敷衍することはできない。
- コレステロールは高めが長生きという見解は、一般住民による調査結果であり、慢性肝疾患や虚弱体質といった住民の除外が十分行なわれていないため、結論づけることは危険である。高リスク症例が治療を放棄することを憂慮する。また日本人では総コレステロール値が低い高血圧例では脳出血の発症リスクが高いという成績がある。
- 脂質異常症の基準を一律にLDLコレステロール140以上とすることは不要な治療を促す要因となりかねない。性差を考慮し、かつ治療必要性・管理基準と整合性のある診断基準が必要と考える。
- 動脈硬化性疾患発症のリスクはコレステロール値のみでなく、高血圧、糖尿病、喫煙、家族歴などの他の危険因子を考慮したトータルな生活習慣病の管理が重要である。
日本の基準は厳しすぎる?
日本は欧米に比べて厳しすぎるという意見もあります。アメリカではLDLコレステロールの薬物治療開始ラインは190㎎/dl、生活習慣の改善目標値が160㎎/dlという話です。
また日本ではコレステロール低下薬の市場規模は3000億円超という事実、1990年有名なスタチンの発売直前に基準値が引き下げられたという事実とともに、日本動脈硬化学会には製薬会社から多額の寄付金が寄せられているという情報もあり、一考に値すると考えます。
コレステロールと食事の関係
2015年にアメリカで食事のコレステロール摂取制限は必要ないとの発表があり、厚生労働省も『日本人の食事摂取基準2015年版』ではコレステロール摂取の上限値がなくなりました。
コレステロールの大半は体内で合成される
食事中のコレステロールは吸収率に個人差が大きいということもありますが、そもそもコレステロールは肝臓で合成することが可能で、食事から摂取されるものが20~30%なのに対して体内で合成されるものは70~80%になるのです。
コレステロール摂取量=検査値ではない
そしてコレステロールは身体に不可欠なものでもあるので、摂取量が少なければ合成が増え、摂取量が多ければ合成が減少するというように調節されており、摂取量がそのまま検査値に反映されるわけではないのです。
それでも食事には気を付けましょう
それでは食事について何も気にする必要がないのでしょうか?
血中コレステロール値に関与しないのだから食品のコレステロール含有量に神経質にならなくてよいとしても、動脈硬化を引き起こす原因は血糖値や中性脂肪、高血圧など複数あります。
動脈硬化の予防という目的からは食事の重要性は疑う余地のないところでしょう。
コレステロールが高かったら?
いろいろな病気を考慮し、治療を選択
一般的には他の併存疾患やリスクを考慮して治療方針を決めます。
冠動脈疾患の既往があれば二次予防として、糖尿病・慢性腎臓病・非心原性脳梗塞・末梢動脈疾患がある場合もハイリスクグループとして、厳重な管理が推奨されています。
食生活改善
ハイリスクグループに入っているということは、それまでの生活習慣になんらかの改善点があるということなので、食事について見直すことがまず大事だと思います。
薬物治療も慎重に
既往のある患者さんには二次予防として薬物治療をすることが多く、できるだけ薬は使いたくないと思ってはいますが、このような患者さんに薬なしで再発を予防しましょうと言うには勇気と覚悟を必要とします。
また、管理目標とされる数値が厳しすぎて達成しようとすると投与量をかなり増やさなければならないケースもあり、そこにも疑問を感じています。
コレステロール異常だけなら、生活習慣などの改善を優先
コレステロールだけの異常であれば、薬はお勧めしません。
もし喫煙したり多量の飲酒をしているのであれば、それらを改善するほうがその人の健康に寄与するはずです。
とくに女性で閉経後に急にコレステロール値が上がることがありますが、この場合も薬はお勧めしません。
閉経にともない急激にエストロゲンが減少するためですが(エストロゲンには細胞のLDL受容体の発現を促進する、肝臓のLDL受容体数を増加させる等の働きがあるためと言われます)、この時期の高値は冠動脈疾患の発症につながらないと考えられています。
薬を飲むことは、健康になることとは違います
薬を服用すれはほぼ確実にLDLコレステロール値は低下します。(HDLコレステロール値を上げる効果はあまりありません)
しかし数値の改善がその人の健康を表していると考えてよいのでしょうか。
薬で介入した場合に抑制されるとされるのはおもに冠動脈疾患の発症であり、そもそも日本人(とくに女性)では欧米人に比較して少ない疾患です。
つまり統計的には少ない狭心症や心筋梗塞を予防するために、長期の通院と服薬をすることになるのです。
それらを検討し、起こりうる薬の副作用も考慮したうえで個別に治療方針を決めるべきと考えます。
コレステロールを下げるというよりも、動脈硬化の改善を
コレステロール低下治療は、致命的となるような動脈硬化を予防することです。
LDLコレステロールが高いという結果が得られたら、じっさいに動脈硬化がどの程度かを把握して、数値を改善させることよりも動脈硬化そのものを改善させるのが本来的に、理にかなっていると考えます。
動脈硬化改善に取り組まれる 真島 康雄 先生
そのような治療を実践されているドクターのご紹介です。
動脈硬化を簡便に視覚的に評価する手段として、プラーク形成の有無をエコーで確認します。
頸動脈エコーは広く行われていますが、こちらでは頸動脈だけでなく右鎖骨下動脈、腹部大動脈、大腿動脈のプラークを計測します。
そして厳格な食事療法を実践しながら最小限の投薬で経過観察すると、プラークが消退していったケースも何例も確認されています。
この真島先生によれば、プラークのコアになる脂質は食事由来の脂肪分であり、甘いものの過食やアルコール多飲が血管内皮細胞の状態をわるくするとの考えからそれらを制限し、マクロファージの活性を上昇させることでプラークの消退も可能だということです。
真島消化器クリニック公式ホームページ
http://majimaclinic22.webmedipr.jp/index.html
生活習慣の改善と食事療法が重要
LDLは酸化することでプラークの元になるので、生活習慣のなかで酸化ストレス(喫煙、肥満、過度の運動、ストレスなど)を避けることが重要です。
適度な有酸素運動は、血流量の増加・代謝の向上などによりHDLコレステロールを増加させることができると言われています。
中性脂肪や血糖値に関しても減少させることができます。
〈日本動脈硬化学会の推奨する食事〉
- 食物繊維の多い食品(玄米、七分づき米、麦飯、雑穀、納豆、野菜、海藻、きのこ、こんにゃく)を増やしましょう。
- →コレステロールの排泄量を増やすとされています。
- n-3系多価不飽和脂肪酸の多い青背の魚や、n-6系多価不飽和脂肪酸の多い大豆を増やしましょう。
- →青魚のDHAという成分には血管の弾力性を高めたり、赤血球の柔軟性を向上させる効果があり、EPAという成分には血栓を作りにくくして血流をよくする効果があります。
- 大豆に含まれるたんぱく質と食物繊維には、コレステロール低下作用があるだけでなく、納豆では納豆キナーゼという酵素が血栓を溶かし、過度の血液凝集を防いで、血液をサラサラ状態に維持します。
- 飽和脂肪酸(脂身のついた肉、ひき肉、鶏肉の皮、バター、ラード、やし油、生クリーム、洋菓子)や、工業的に作られたトランス脂肪酸の多い食品(マーガリン、洋菓子、スナック菓子、揚げ菓子)は控えましょう。
- →飽和脂肪酸はエネルギー源にもなりますが摂りすぎると肥満、動脈硬化につながります。
- トランス脂肪酸は動脈硬化のリスクを上げるため全面禁止されている国もあるくらいなのですが、日本は規制が緩くほとんどのパンやお菓子に含まれているので要注意です。
- コレステロールの多い食品(動物性のレバー、臓物類、卵類)は控えましょう。
- 基本的には、日本食(魚、大豆、野菜、未精製穀類、海藻を十分に、乳、果物、卵を適量に、肉の脂身、バター、砂糖・果糖を控える。ただし減塩で食べる)を意識しましょう。
よいと言われているものでも食べ過ぎは禁物、肥満の改善がなにより重要です。
酸化LDLとならないように、抗酸化物質であるビタミンA、C、Eやポリフェノールをたくさん摂取することが勧められます。
ビタミンA・Eは緑黄色野菜、魚や鶏肉、レバーに多く含まれます。
ビタミンCは意外に摂りにくく、カラーピーマンやブロッコリー、じゃがいもやさつまいも、果物では柑橘系、キウイ、いちご、柿などに多く含まれます。
コレステロールが低かったら?
脂質異常症の診断基準には総コレステロールとLDLコレステロールの下限値は示されていません。
人間ドックではLDLコレステロール59以下で要医療とされていますが、じっさいに病院に行ったとしてもなんの指導もされないことが多いかもしれません。
コレステロールが低いことも問題です
しかし上述のようにコレステロールには大切な働きがあるため、低すぎればなんらかの支障は起こり得ます。
分子栄養学やオーソモレキュラーと呼ばれる分野では(私自身はあらたな医療の流れととらえています)、低すぎることから生じるさまざまな問題に焦点を当てています。
細胞膜の機能と神経伝達に関与し、胆汁酸やホルモンの原料となっているわけなので、不足した場合にはそれらに起因する症状が広範囲に生じてくる可能性があります。
コレステロール値が低くなる原因を探しましょう
コレステロール低値の場合、その合成にかかわっているのもタンパク質なので、まずタンパク質をしっかり摂ってそのタンパク質の消化吸収をよくするために胃腸を整える、合成の場である肝臓の働きをそこなうような原因がないかどうかを見直すことが必要と考えます。
後期高齢者の場合
私が診療するずっと以前からコレステロール低下薬を続けていた高齢の女性患者さんがいました。
治療開始にいたった検査データはもはや不明。
肥満・喫煙・飲酒はなく他の疾患もなく、その薬を飲んでいたから80代まで長生きできたのでしょうか?それはわかりません。
前期高齢者(65~75歳)では薬による動脈硬化予防はエビデンスありとされていますが、75歳以上で既往がなければ個々の判断にまかせられています。
ただただまじめに通院されているその患者さんに、どのように説明すべきか考えながら(いきなり中止を勧めると見捨てられたように思われるケースもあります)減薬していったところ、「もう薬はいいと思うんですよ」とご本人から穏やかに話されたため中止しました。
数年経過していますがLDLは高めで安定しお元気です。